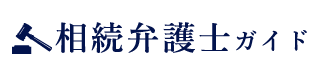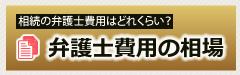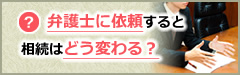遺言書は自分の意思で書かれていなければ無効になる
遺言書というのは、自分の意思で書かれていなければ効力が発生することはありません。
遺言というのは、被相続人自身の最後の意思表示と言い換えることができるため、そこに被相続人の意思が反映されていないのであれば、当然ながら無効となります。
遺言書においてよく問題となるのが、強迫によって遺言が書かれていなかったのか?遺言を書いた時点で被相続人に遺言能力があったのかどうか?といったところです。
それではそれぞれ詳しく見ていきましょう。
強迫などによって遺言が書かれていた場合
相続人やその他の利害関係者から強迫などがあり、被相続人の意思が反映されていない状態で遺言が書かれたことが明らかとなった場合、当然、その遺言は無効となります。
さらに、被相続人に対して強迫をしていた者については、相続人としての地位までも失うことにもなります。

もちろん、強迫だけでなく遺言書の偽造や変造についても同様の扱いがされることになります。ただし、この場合、偽造・変造前の遺言については有効となる場合もあります。
とはいえ、どこからどこまでが偽造・変造であるのかを判断するのが困難な場合もあり、裁判上の手続きにまで発展してしまう可能性が高いです。こういった場合は、専門家の力を借りるのが無難といえます。

○参考ページへリンク
相続人として資格を失うことを相続欠格といいます。相続欠格となった場合、子供がいれば代襲相続となります。
→相続欠格とは?相続人の資格を失う場合
遺言書は偽造・変造以外にも、隠していたことが発覚しても相続欠格となる可能性があります。
→遺言書の隠匿と相続欠格事由
被相続人が未成年で遺言能力がなかった場合
遺言というのは、何歳であっても残すことができるわけではありません。遺言適格年齢は民法によって満15歳以上と定められていますので、15歳未満が書いた遺言はすべて無効となります。
15歳未満の場合、その子の両親が法定代理人となっていますが、たとえ法定代理人であっても、遺言については関わることができません。というのも、遺言というのは本人の最終的な意思であるため、代理によってまかなわれるべきではないからです。
被相続人が認知症などで遺言能力がなかった場合
遺言を作成した時点で、被相続人が認知症などによって遺言書に自身の意思を反映させることができていなかった場合、その遺言も当然ながら無効となります。
被相続人が認知症の疑いがあったような場合は、遺言書が作成された日付と、その時点の通院記録や生活状況などによって最終的な判断がされることになります。
こちらは遺言無効を争う典型的なパターンと言えるため、争いを防ぐためにも遺言書作成当時の被相続人の状況については、しっかりと記録しておくようにしましょう。